SATはSATは,College Boardという団体が主催するアメリカの高校生を対象とした大学進学適正試験です。アメリカの大学の入学試験の学力試験の中で最も大事なものと言っても過言ではないでしょう。
今回はSAT数学がどんなものか、テスト範囲と形式、そしておすすめの参考書を紹介していきます。
SATの重要性
アメリカの大学はテストで測られる学力よりも、日々の積み重ねである成績や課外活動、ボランティア活動やスポーツでの活躍をとても重視しています。
しかしトップ校の入学許可率は5%程度です。1人ずつの願書をじっくり見るわけにもいかないので、SATの点数で足切りに合うことは容易に想像できます。


SATは難しいテストではなく、勉強すれば確実に高得点が狙えるテストです。
私もSATを留学中に3回受けましたが、3回中2回は数学で満点を取ることが出来ました。
SATはいつ受けられる?

SATは年に7回実施されていて一番良いスコアを提出することができる
⇒ 日本の入試の一発勝負のようなものではない
また全世界でも受験が可能になっています。私も日本のインターナショナルスクールで土日にSATを受けました。
アメリカでは、自分の通っている高校でテストが土日に受けられます。
試験監督も学校の先生で、知っている人に囲まれて受ける
⇒ 緊張感はなくみんなリラックスしている
SAT数学のテスト構成
数学のテストは2つのセクションに分かれています。1つ目は計算機なし、二つ目は計算機ありです。
1パート(計算機なし)
計算機の使用が不可能で20問のテストを25分で解くパート。15問は選択問題で最後の5問は答えを記述する。
最初の問題は四則演算などの小学生でもできる問題が並んでいます。
4択問題になっている
⇒ たとえ計算ミスをしても回答に選択肢がない時はすぐに気づくことができる
最後の問題も構える必要はなく、普通に計算すれば答えが出てきます。
2パート(計算機あり)
計算機の使用が可能で38問を55分で解くパート。最後の5問は答えを記述する。
こちらも計算機を使う問題ではありますが、計算機を使わなくてもできる問題は多いです。
計算ミスをしないためには計算機を使うのが良いかもしれません。
記述問題は出題されないから証明問題などには触れなくて大丈夫!数学に出るのは3つの範囲

①問題解決の能力を見るもの
②データからの解析、分析
③台数や幾何学の基礎的な問題
問題解析・データの分析
問題解決と、二つ目のデータ解析については部分では日常生活や、科学で使うものについて問題を解く
つまり比率問題や、%問題が頻出と言ってよいでしょう。
アメリカの高校では日本の高校に比べて統計の授業が充実しているので、少し対策が必要になると思います。
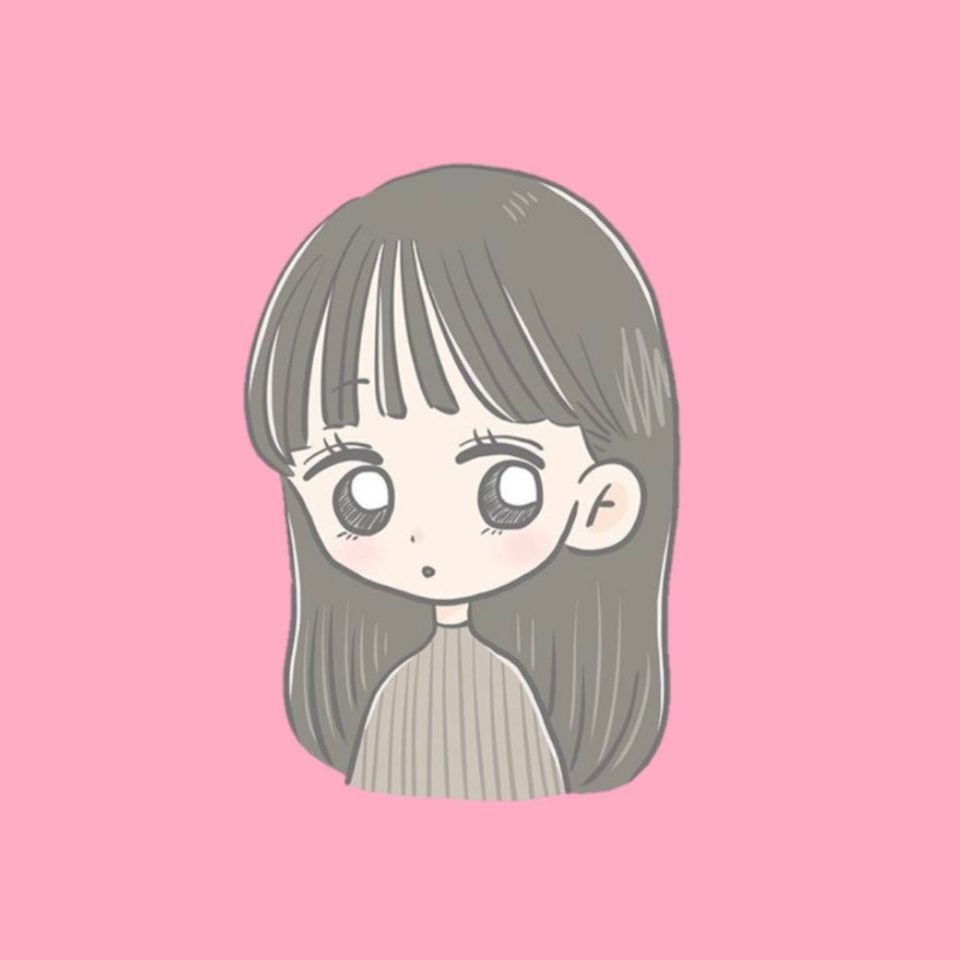
資料の読み取りがおおいかな。
台数・幾何
代数では一次関数と簡単な二次関数が出る。幾何学問題も三角形の面積が出ることもあるくらいのレベルで日本でいうと中学生くらいで習うことが多かった。
最後のセクションを除いて4択であるため、自分で答えを出してから答えが違ったら、見直しとして、もう一度解くこともできます。
最初に公式集で丁寧に三角形の面積の出し方や、球の体積の出し方がかかれている
⇒ 公式を覚える必要がない!
計算に自信がない人も大丈夫です。電卓を使えないセクションでは簡単な計算しか出てこないため、心配は無用です。
過去問を解きまくろう
SATで1番大切なのは、過去問に慣れることです。
出る問題のパターンは決まっている
⇒ 何度も過去問を解くことで自然とわかってくる
時間を図ることで本番焦ることもなくなるり、過去問を解くことで自分の苦手な分野が見えてくると思います。
おすすめの過去問
The Official SAT Study Guide 2020
The College Boardが出版する唯一の公式ガイドになっているので、1人1冊は必ず持っています。
問題は8回分収録されていて、試験形式に近い練習ができます。
Princeton Review
こちらは他の参考書に比べると使われている英語がわかりやすいです。
SATでの重要ポイントも詳しく解説されているので、問題攻略から学びたい人にはお勧めの1冊です。
5つのテスト(そのうち一つはオンライン)が含まれているので実践演習も積みやすくなっています。
まとめ
今回はSATの数学がどんなものかを紹介していきました。
SATはアメリカの大学、日本の大学でも使えるものなので、勉強して損はないです。
SAT数学であれば、勉強を始めるとすぐにスコアがアップすると思います。ぜひ興味があれば挑戦してみてください。



コメント