私は高校生の時に1年間アメリカに高校留学に行っていました。
私はバーモント州という田舎の高校に留学していたのですが、隣にはリベラルアーツで有名なミドルバリー大学がありました。大学は高校と提携していて、毎年優秀な生徒10名ほどを大学の授業に招待してくれます。
科目は特に指定がないため、高校にはないロシア語や哲学など自分の興味のあるコースを取る人もいれば、難易度の高い大学の数学や物理に挑戦する人など様々でした。
私もミドルバリー大学で化学の授業を受講したのでその時の授業の様子や成績の付き方について紹介していきます。


大学の授業の選び方
それぞれの科目の授業に多くのコースが存在します。
- 0101 World of Chemistry
- 0103 General Chemistry
- 0204 Organic I Struct &Reactivity
- 0301 Medicinal Chemistry
- 0322 Biochemistry of Macromolecules
- 0442 Advanced Organic Chemistry
これは化学の授業の一部抜粋ですが、24種類の化学のコースがあり、それぞれに番号がついています。番号は難易度を表していて、おおよその目安として100番台が1年生、200番台が2年生、300番台が3年生になっています。
他大学でも同じシステムを導入していることが多いです。
そして好きな授業をとれるわけではなく、300番台や400番台を受講する条件として、100番台の授業を受講していることなどが出てきます。
1つ1つの授業にCourse description があっていつ開講日時や詳しい授業内容が大学のWebサイトに載っているためそれを参考にしながら、撮る授業を慎重に決めるのが良いと思います。
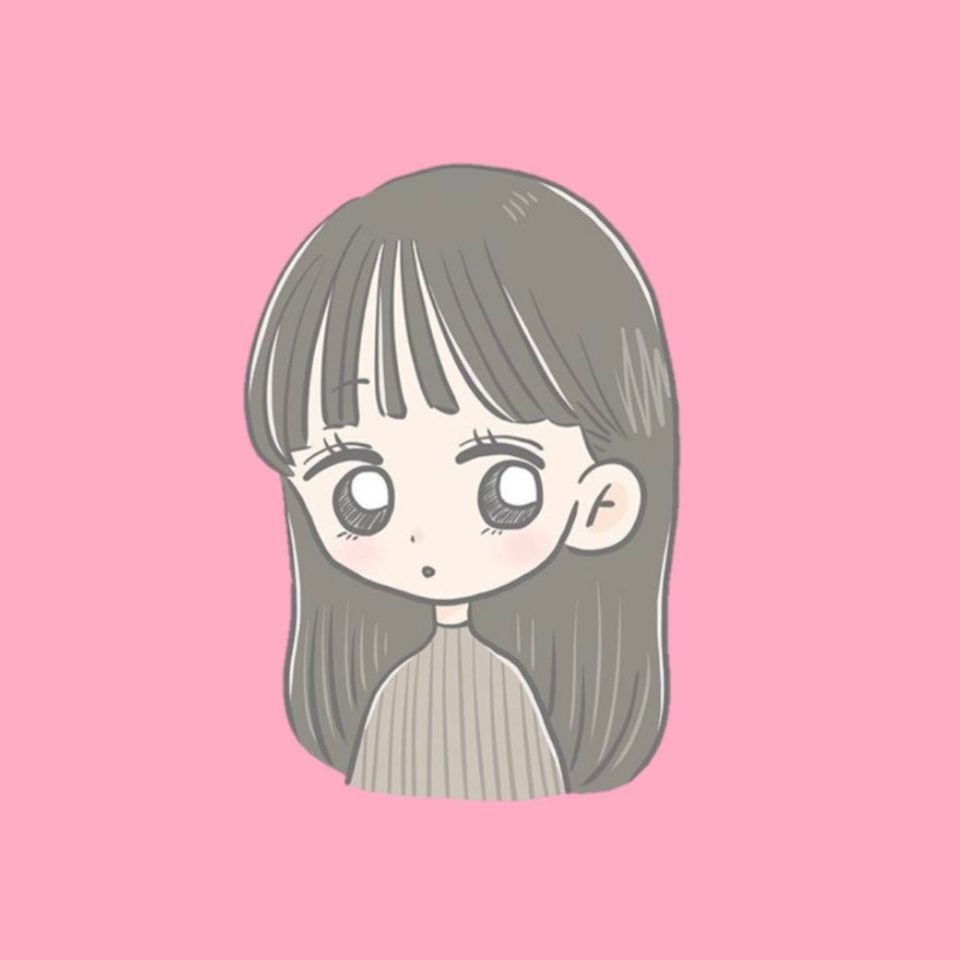
カウンセラーと相談しながら決めていけるといいね。
授業の様子と雰囲気は?
講義:50分×週3
実験:3時間×週1
私の取った化学のコースは週3回、朝の9時から50分の講義と、週に1回午後1時からに3時間の実験がありました。
日本の大学との違いは講義の時間が短くて、週に3回ある事だと思います。日本の場合ほとんどが90分授業が週に1回になっています。
⇒1年生が取る化学の授業は文理関わらず多くの人が受講していて、内容も専門性の高いものではなかった印象を受けました。
講義は映画館のようなつくりの教室になっていて、ひじ掛けから自分のテーブルを出して授業を聞きます。
朝であったため、サンドイッチ片手に受ける人やリンゴを持っている人、コーヒーを飲んでいる人など様々でした。教授も毎日コーヒーを飲みながら授業を行っていました。
授業のレジメやスライドはあらかじめ配られているため、それをパソコンで開きながら先生の板書をノートに書いていきます。少しでもわからないところ、疑問点があれば授業中であっても手を挙げて質問をすることが推奨されていました。
課題や宿題は量が多い
1週間に1度60分程度のオンラインの宿題が出されます。また、実験が週に1度あるため、そこで実験データをとって家で考察してくることが多かったです。
授業の予習と復習は宿題とはいわれませんが、必ず行うべきです。
大学の授業は進みが早いので1回でもおくれを取ると、授業をきいていても理解できずに板書をひたすら写すだけの作業になってしまいます。授業中に多くのことを吸収するためにも予習と復習は必須になります。
成績の付き方
実験:15%
中間テスト:25%
期末テスト:50%
成績の付き方は上記のようになっています。中間テストと期末テストは、授業中に50分間行われます。9割以上取らないとAがもらえないので評価は厳しくなります。
テスト勉強は最低でも2週間前から始めて備えるのが必要になります。ちなみに私はA-が最終的な評価でした。
高校生は大学の単位認定をもらえるのか
大学と提携したものは高校の単位として認められます。つまり、難しすぎるものを取ってしまうと高校のGPAが下がってしまいます。
大学の授業は課題がとても多く、期末試験期間も高校とずれているのでそれなりの覚悟がないと大学の授業を取るのは大変だと思います。しかし大学の単位が先取りできるので、大学生になったときにとれる授業の幅が広がります。
アメリカの大学生は夜中まで勉強
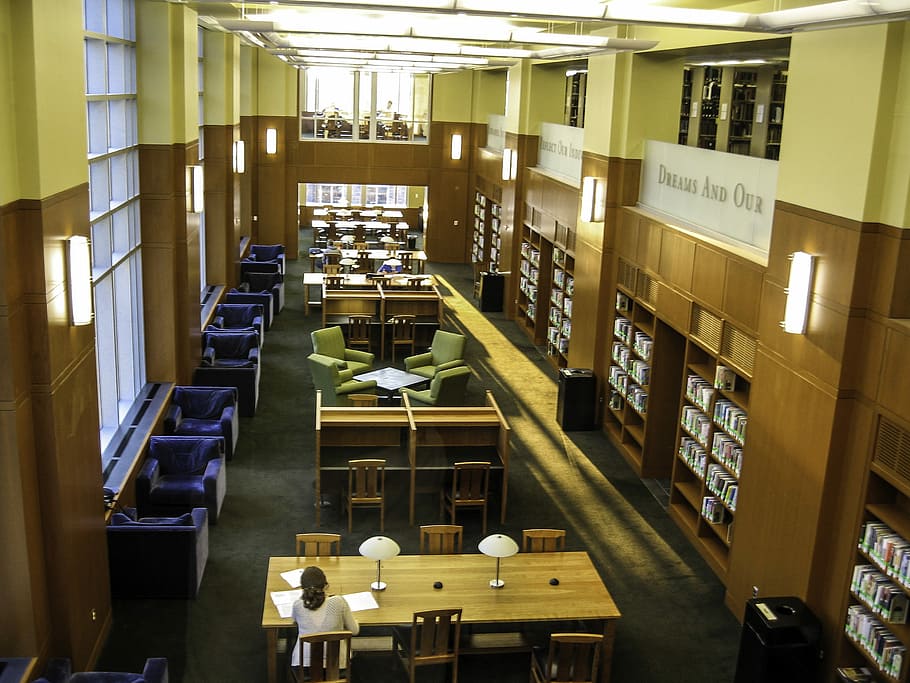
アメリカの大学生はGPAを高く保ち、夜遅くまで必死に勉強します。図書館は大学内にいくつも存在し、24時間あいている図書館もあります。
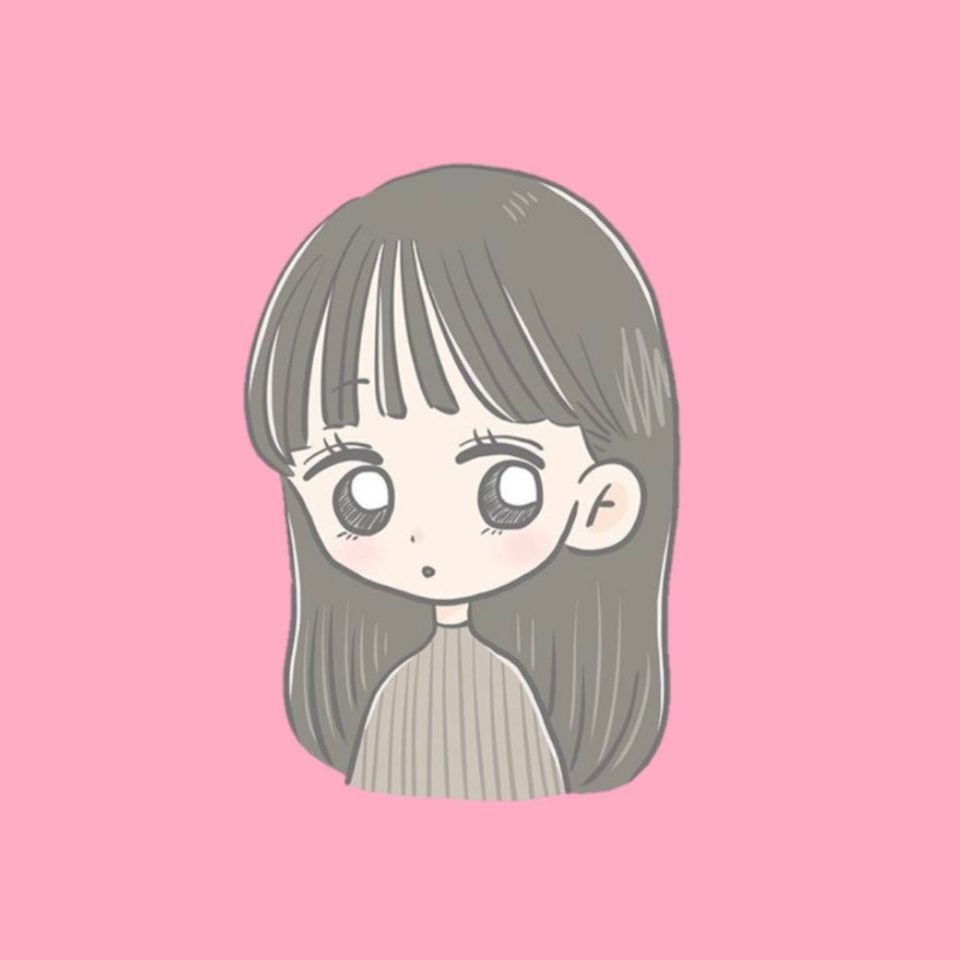
夜中に図書館に行っても誰かしら勉強しているよ。
なぜ勉強を頑張るのか
アメリカの大学は学費が高くて有名です。私が授業を受けていたミドルバリー大学も私立の大学で、学費や生活費を合わせると毎年700万円以上かかるといわれています。高い学費を払ってくれている親のためにも勉強を頑張っている生徒が多かったです。
就職でもGPAが重要視されるため、4年間を通して常に気を抜けない状態にあるのがアメリカの大学生です。
アメリカと日本の大学生どちらが賢いのか
私は高校留学しているときは、日本の高校生のほうが難易度の高い数学を行っていると感じていました。
アメリカ人:学校の宿題だけ
日本人:宿題のほかに塾に行って遅くまで勉強
アメリカの大学受験に使うSATも受けたのですが、最初の問題には三角形の面積の問題も出されていました。
しかし、大学のランキングを見るとアメリカの大学が上位を占めていて、東大であっても1桁台に入ることは不可能になっています。
2013年に集計された日本の大学生の学生生活実態調査概要報告のデータによると、一日あたりの勉強時間が文系の学生で約28分、理系の学生で約48分となっているようです。平均で6時間ほど自習をするアメリカ人との差は歴然としています。
まとめ
アメリカの大学生はとても授業に熱心であることがわかります。日本人のように授業をきったり学校に行かないことはありえません。自分もアメリカ人を見習って頑張りたいと思わせてくれます。




コメント