私は高校2年生から3年生にかけての1年間アメリカのバーモント州に留学していました。留学先では、現地の高校生と一緒に授業を受けていました。
今回は化学の授業がどんなものだったか紹介していきたいと思います。
化学の授業の種類があるのか

化学の授業は私の学校は2つしかありませんでした。Chemistry1とChemistry2です。基本的に秋学期にChemistry1、春学期にChemistry2が開講されています。ほかの大きな学校に行くとAPといって大学の単位をとれる授業も開講されていることがあります。
私の高校の隣にはMiddlebury collegeという大学があったため、私は秋学期はChemistry1、春学期は大学で大学生と一緒に授業を受けることにしました。大学での化学の授業についてはまた違う記事でまとめたいと思います。
化学はどんな人が取っているのか、取らなくても卒業できる?
アメリカの授業は英語や数学を除いて基本的に9年生から12年生まで取ることができます。実際に私の化学の授業には9-12年生の男女がいました。物理は男子が多い印象でしたが、化学は男女比は約1:1だったように思います。
時間割は自分で組むため、化学は高校の中でどのタイミングでとっても良いのです。自分が化学が好きであったら下の学年の時に取ればよいし、苦手であったら取らなくても大丈夫です。化学は高校に3人の先生がいて化学が取りたい人が柔軟にとれるように3つの時間帯で開かれていました。先生の好みによって授業を選択している人も中にはいました。
アメリカの高校の化学の授業の様子

授業は毎日あるのか
授業は100分間で学期中は毎日授業がありました。休憩があることは基本的にないと思ってい良いです。しかし、トイレに行くことや水筒に水を汲んで売ることなどは許されています。そのためみんな自由に先生に許可をもらって教室の外に出ることが多かったです。
授業が少し早く終わってもチャイムが鳴るまでは教室から出られない決まりになっています。授業が早く終わると、アメリカのおもしろ動画サイトの動画をプロジェクタに流してくれていました。みんなは一刻も早く教室から出るために動画を見るときにはリュックに荷物をまとめて腰を浮かせて待っていました。
授業はどう進んでいくか
授業は座学と実験に分かれています。化学は教えるべきユニットが全国共通で決まっています。そのため基本的には座学で、先生がホワイトボードに書くことを自分でプリントかノートに埋めていって授業が進みます。
その他にも、先生がYoutubeのわかりやすく説明している人の動画を引っ張ってきてみんなで見たり、化学で出てくる現象を動画で見ることもありました。
座学の補助として、2人組で実験をする日もあります。日本でやる実験とほとんど同じです。例えば4つのビーカーの中に、砂糖や塩などの白い粉物質が入っていてそれぞれが何かを実験を通じて調べていくような簡単な実験です。
簡単な実験が多いし、失敗すれば何度もやり直すことが可能になっています。また実験に失敗したからと言ってペナルティはなく実験のレポートを出す必要もないため楽しく実験をすることができました。
先生を補助するTAは学生
化学の授業にはTAというティーチングアシスタントがいました。先生の補助をする役目を担っています。化学にもTAがいてその人は12年生でした。前の学期に同じ化学の授業を受けてい自分がTAをやりたいと思ったら申し込むことができます。大学のように給料が出るわけでもありませんが、良い成績をとれることは確かです。
そのため、卒業までの単位を取り切っている12年生がGPAをあげるためにTAをやっているイメージでした。生徒はTAに気軽に質問することができるのです。
成績の付き方は

宿題:15%
ファイナルテスト:50%
授業参加度:10%
小テスト:25%
となっていました。また、Aを取るには9割以上の点数を取る必要があります。ちなみに私は途中から慣れてきたこともあってAを取ることができました。最初は特に気にしていなった小テストも途中からはみなと一緒にテストの点数に一喜一憂するほど成績に敏感になっていました。
なぜアメリカ人が成績に敏感なのかについては次の記事を参考にしてみてください。
全てで9割以上を取るのは難しいため、救済処置もあります。何か先生が質問をした時に手をあげて答えたり、解き方をみんなに紹介することでボーナス点がもらえます。これは成績が命であるアメリカ人にとって重要なことなので授業中は挙手をする人がほとんどでした。
宿題は毎日出される
宿題はすべてオンラインの教材から出ます。そして自分で答えが合うまで何回も挑戦して大丈夫です。
宿題の解説は先生が授業で行ってくれます。宿題は基本的に毎日出るので該当の場所のクイズをオンラインで受けるだけでとても簡単でした。
テスト前は猛勉強
テストは2週間に一回ずつくらい、その他に中間テストと期末テストがありました。テストは半分が選択問題で残りの半分が記述問題でした。テストの前は自分のノートやオンラインの教科書を見返すことで、平均で90点以上の点数が取れました。
期末テストでは範囲が全てであったので、1か月前から少しずつ対策をし始めてまとめノートを作っていました。
日本の化学との比較

日本の化学よりも簡単な理由
正直に言って日本の化学のほうが難しいです。日本の難易度と照らし合わせると中学の化学と高校の化学基礎の中間の難しさであったと感じます。
基本的に理論化学で有機化学や無機化学は大学に入ってから専門的に勉強したい人が深く勉強するため、高校では基礎的なところだけを学んで自分の中で化学が好きかどうかをわからせているイメージでした。
化学は選択科目のため取らない人もいて、そういう人は社会や文系科目を取っていました。
計算が面倒くさい
日本ではある程度原子の質量など計算されやすい数に調整されていますが、アメリカでは関数電卓を使うことが許されているため、計算が複雑になることが多いです。
例えば、日本では水素は1、炭素は12として質量数を取るため基本的に小数点以下の質量は切り捨てています。しかしアメリカでは小数第2位、水素に関しては小数第3位まで有効数字として使うことがほとんどで式が長くなる傾向にありました。
日本ではある程度計算が複雑になっていくと何か間違えているかもしれないと予想できるのですが、アメリカではそういった予想はすることができません。アボガドロ数などの指数が大きくなるものは10の累乗が何になるのかわからなくなることがあるので手計算も混ぜながら計算していました。
番外編
実験は眼鏡が合わない
実験で使う保護用メガネがずり落ちてきて使い物になりませんでした。なぜなら外国人用に作られたものになっているので鼻が高くなっていて、鼻の低い日本人にはフィットしません。そのためさりげなくいつもゴーグルの保護メガネを使う必要がありました。
まとめ
今回はアメリカの高校の化学の授業についてまとめてみました。日本よりも簡単であることが多いので焦らずに一つずつ単語を覚えていけたらすぐに成績が良くなると思います。ぜひ留学中も悔いの残らないように勉強してください。
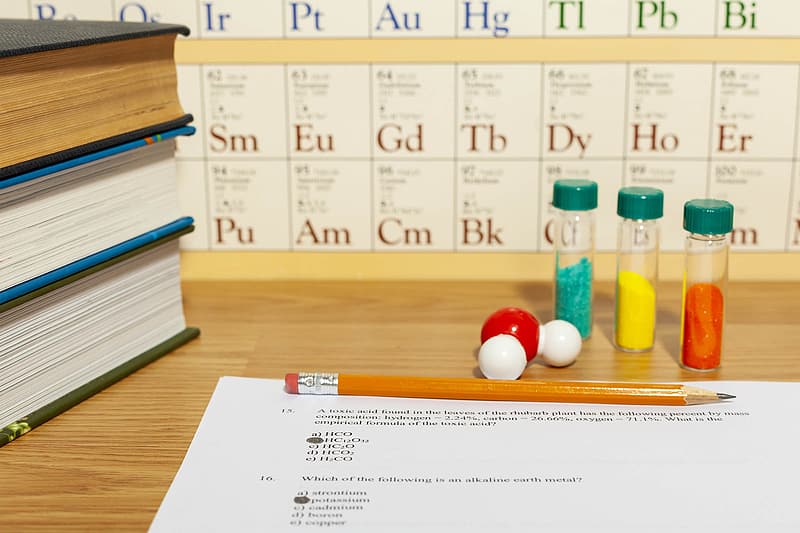



コメント